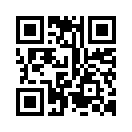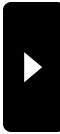『新郎新婦の入場です! 』ヤノミさんのスタンダップ・コメディで笑い泣き(涙)

ああもう、今年一番笑いましたよ。否、2024年に入って、こんなに笑ったのは、初めてです。
(いま12月なんだけど。寂しいぞ。客観的に、それは寂しいぞ、自分)
今年の2月に続いて、大分市のアトホールでの小心ズ・ヤノミさんの舞台。大分出身のシルク・ドゥ・ソレイユ登録アーティストであり、俳優であり、そしてスタンダップ・コメディアンでもあるヤノミさんの今回の公演は『新郎新婦の入場です! 』抱腹絶倒の(決して誇張ではない)スタンダップ・コメディでありました。
いや、本当に、今年初めて(12月にして、今)めちゃくちゃ笑いましたよ。だって今年は年明けから父子でインフルに罹るわ、母も体調崩して入院するわ(介護の申請とかとか、親子で色々乗り越えてきましたね)近しい人たちが次々と逝ってしまったり。そう、最近は、誰かを祝う時間よりも、見送る方が断然多くなってきた事に改めて思い至りました。更に世の中、世界、と見渡せば、言葉を失うことばかりじゃないですか。とても祝えるような気分ではなかった。
忘れていた。結婚披露宴が、こんなに面白かったことを。
否、知ってた披露宴よりも解像度が高い、笑いに満ちた空間であった事を知りました。そうか! お父様をもっと注目すべきだったのか∑(゚Д゚)それから、日本独特の? 風習というか、ゼ○シィ歩行とか、知らんことだらけやんか? アメリカァのお客さん方に超受けた和製英語とか、たしかに、冷静によく口に出来るよなその単語? ってのが日本では定着していたり。色々と目から鱗の、教養溢れるステージ。ヤノミさんは何百組もの披露宴の司会をこなしてきた上にその観察眼と洞察力(この司会者、油断ならない……)しかも、恥かさーの大分のお客さんたちを巧みに巻き込みながら(実はそんな予感がして、今回は座席を少し後ろに取りました。以前、せやろがいおじさんのLIVEの時に、最前列おったらめっちゃいじられたからw)腹が引き攣る笑い声が響く、あっという間の1時間でした。
そんな今日の時間は、自分にとって、なんやかやあった2024年の清めの時間だったというか。
笑うって、心の中の澱んだ何かを祓う力があるのかもしれませんね。
いや、色々あったは確かですが、良い事もありました。そこに、ヤノミさんが「笑い」を加えてくれた思いでございます。素晴らしいスタンダップ・コメディを、ありがとうございました!
Posted by にいさん at 2024年12月21日 20:56
打越正行さんを偲ぶ

那覇市泊に住んでた頃。時々夜中の時間帯に、中部方面から58号線を通って帰る時。あの爆音を鳴らすバイクの群れとよく出くわしました。(今思うと、なんでまた「よく出くわすシチュエーション」になったのか? と自分に突っ込みたいところはありますが)その「群れ」のそばに、彼らにくっ付くように、原チャリを走らせる風変わりな男性がいました。明らかに周りのヤンキー達とは纏う空気が違う、とにかく風変わりな男性が。
あれは一体何者だ。
数年後、打越正行という人の『ヤンキーと地元』という本が話題になりました。早速私も購入して読みました。
驚きました。ここで書かれている著者の行動。原チャリに乗って後ろから付いていく(前を行く彼らよりも)大人の男性は、まさにあの日ゴーパチで目撃した彼でした。
参与観察。それが彼のやり方で。最初は彼らヤンキーのパシリから始まって、次第に彼らの心を開いていき、仲間として受け入れてもらい、じっくりと彼らの言葉を記録する。彼らが普段、解体屋などの肉体労働をしている身の上であるという話しや、風俗の現場の話し、その場に集う若者たち、ひとりひとりの自分史が浮かび上がってきて、更には沖縄が抱えさせられる産業構造にまで話しは広がって。その構造の底にある生活の過酷さ。所謂ヤバい領域にまで。そんな拡がりと奥行きのあるフィールドワークの力を感じさせられた一冊。
外から沖縄に来た人間が、同じく外からやってきて、すっかり島ないちゃーやさ等と、沖縄に染まった気持ちになっていた自分などよりも、ずっとずっと沖縄の深みに入り込んでいた。もしかしたら、羨望のような眼差しで、彼を見ていたかもしれません。
本当に、身近な知り合いなどではなくて。一方的に目撃して、一方的に本を読んで(Twitterで一応相互フォローしてた)勝手に近い場所にいるような気持ちになっていたという、いちファン、いち読者でありましたが、昨日の訃報に驚きつつ、今は、ただただ、ご冥福をお祈りするばかりです。
誰かと打越さんについて、あの本について、話したくなってしまいました。いろんな追悼の仕方がある事でしょう。さっきTwitter(X)で、教え子の方がホワイトボードに書いた言葉に思わずもらい泣き。沖縄だけでなく、日本のあちこちで、愛されてますね打越さん。
いつか、ゴーパチ以外のどこかで、お会いしたかったです。会いたい人には会える時に会っておけ、という教えでしょうか。
Posted by にいさん at 2024年12月11日 20:42
映画『シビル・ウォー アメリカ最後の日』Amazonプライム・ビデオで配信開始
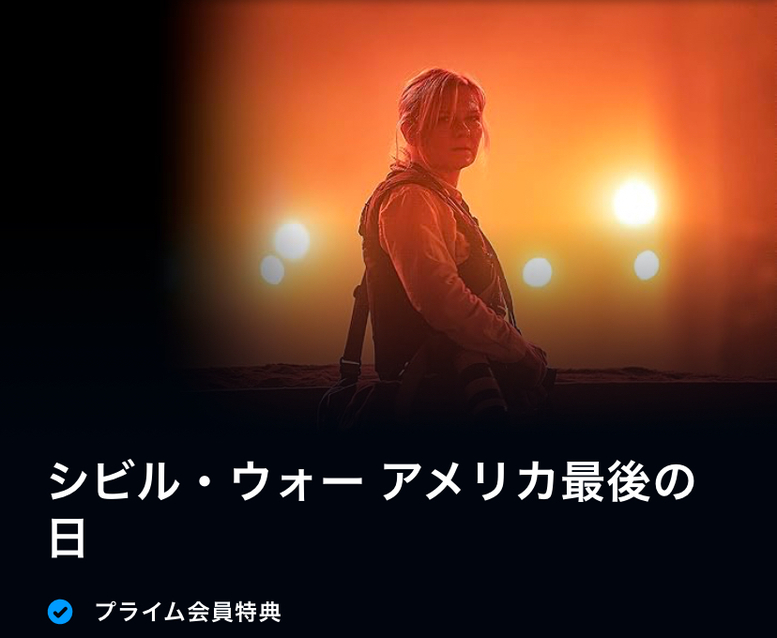
ネタバレは抑え目に書きますが、展開のヒント等には触れるかもしれません。真っさらな状態でこれからご覧になりたい方は読まないことをお勧めいたします。
しかしAmazonプライム・ビデオ。最近益々最新作の配信早くなってない? サブスク間の争いも熾烈さを増しているような……。劇場公開時にタイミングが合わなかった注目作が視聴出来るのは嬉しいですが、え! もう配信すんの!? ってびっくりしてしまいました(汗)
この作品は、連邦政府から19の州が離脱したアメリカにおいて、テキサス州とカリフォルニア州の同盟からなる西部勢力と政府軍による内戦が勃発。決して荒唐無稽なファンタジーでもなければ、英雄が勇気ある闘いで勝利の雄叫びをあげるような「勝者の武勇伝」でもありません。シビアな、凄惨極まりない、殺し合いの現場と、それを記録するジャーナリストたちの姿。
あのA24がこのような大作戦争映画を? って正直最初は思ったのですが、なるほど、A24が制作すると、戦争映画はこうやって描かれるのか。と、ある意味納得させられるような作品でもあり。
それは、まるでドキュメンタリーのような肌触りの、ある重要なスクープインタビューを試みる(3世代の)ジャーナリスト達のロードムービー。
あの家に誰かいる
誰なんだ
わからん
……
お前ら、そんなわからん奴同士で殺し合ってるのか? なんだそれ。いや、この「なんだそれ」の積み重ねこそが戦争の悍ましさなのか。ただ、動くものは撃て(元海兵隊員のアレン・ネルソンさんの言葉が蘇ってきて仕方がなかった)。銃を持った馬○は相手を単純な色分けで引き金を引く。西か東か。そして外国人には見境無く?
こういう奴。いるよな、なんて事を思いながら見ていた。銃(力)を持った気になって、外国籍の人や少数派の人たち、自分よりも弱い人たちへ向けて引き金を引こうとする連中。このような者に持たせてはいけない-という奴に限って銃を握ろうとする。軍隊に憧れる素人ですか? 又は軍隊に染まることで「躊躇いがなくなる」姿もまた背筋が凍ります。危ない素人と迷いなく遂行していく職業軍人。一体どちらがタチが悪いのだろう? 敵と認識した瞬間、交渉が成立しなかった瞬間。躊躇いなく引き金を引くって、やはり軍隊に染まることは恐ろしき事に映ります。(「戦場では敵をグールと思え-と教育されたのです」またネルソンさんの言葉が頭に入ってくる。何度も、何度も)
この、架空の(と思いたい)アメリカでは、大統領が3期目を迎えているらしい。憲法も大きく変えて、痛いところを突かれる恐れがあるのか連邦捜査局は解体し、為政者にとって都合の良いように国家の形を変えてしまった先の風景が、これ。
戒厳令を出すようなリーダー。自分に都合の良いリーダー。権威主義がぷんぷん匂うリーダーは国家を危険に晒すようです。巻き込まれるのは国民。これは遠く離れたアメリカの架空の話し? いいや、そうは思えないな。
あの地獄、絶望の中にあっても、次の世代への眼差しというか、継承のドラマには、僅かながらも光を見た思いがしました。
Posted by にいさん at 2024年12月06日 17:44
ぺ・ミョンフン『タワー』(韓国文学はSFも面白い! )

私たちの社会にも、青いポストが存在し得る事を信じて。
ぺ・ミョンフンのSF小説『タワー』の感想。ネタバレは抑え目に……と言ったところで、ビーンスタークの用語や、その構造は、読んだ人にしか伝わらない事でしょう。しかし、伏せたい部分は伏せながらで。
そこは674階建ての独立国家。
全てが平面の2次元ではなく、3次元で構成された都市国家。
新自由主義なるものを煮詰めて固めて、権力者たちがその野心の分だけ積み上げていったような建造物、建造物、と呼べる閾値をあらゆる点で突き抜けていったようなタワーは雲をも突き抜けていきました。はて? 権力者と書いたものの、ここには確かに「権力機構」は見て取れるにしても、その権力者とやらはどこにいるのか。それはまさかの動物が!? いやいや、そんなわけがあるかい。動物に権力が集まるとか、動物が涅槃の境地に至るとか。そんなおかしな話しがあるものですか。
そんな不思議な、超高層都市国家をめぐる連作短編集です。否、連作短編集の体そのもののごとき構造の国家をめぐる、ひとつの大河小説のようにも思えてきてしまいました。
『東方の三博士ー 犬入りバージョン』なんというタイトルでしょう(笑)このビーンスタークの複雑な権力機構を解明せんと奮闘するミクロ権力研究所の博士たちの奮闘。解明の鍵は、貨幣価値をもつ、あの飲み物が。
『自然礼賛』権力者に不屈に立ち向かってきた作家が、ある時から大自然を描く作風に転向!? 編集者は何とか彼にまた気骨のある反権力の小説をと粘り強く交渉します。その交渉の行方は? そして作家は何故、社会的な作品を封印してしまったのか?
『タクラマカン配達事故』今作における私にとっての最高傑作はこれです! このエピソードに触れるだけでもこの一冊を手にする価値があると言いたい。地獄のような世界の中にあっても、それでも人の心を信じたい。読みながら「おぉ」って声出してしまった(笑)
『エレベーター機動演習』これまた今作ならではの「なんじゃそりゃー」な複雑怪奇な構造物故の軍事演習!? そう。この小説は、戦争下にある国家の物語でもあり。「平和というのは前の戦争と次の戦争の間」という言葉は好きではないけれど。そんな(休戦状態という)緊張感を持つ社会の文学である事に思いは至りました。
『広場の阿弥陀仏』可哀想な、否、言えない。駄目な義兄さんでもいいじゃないか。帰ってこい。それから妹の言う通り。雇われ活動家などで、あんな規模のデモなんか無理だ。民衆の怒りを侮ったり、力を持った者が流すデマを信じてはいけない。こっちへ帰ってこい、兄弟よ。
『シャリーアにかなうもの』敵対勢力との諜報戦もクライマックス。ジェームズ・ボンドの出ない007か? しかしこの国の公務員への扱い酷いな。良い仕事をしても報われない。結構命懸けだったりするのだが。彼は相手のスパイを突き止めて。しかし誰も彼を信じてくれない。孤立無援で最終決戦の行方や如何に!?
付録。という章がこの後続くが、付録と呼ぶには読み応えあるエピソードと用語解説が続きます。ここは読んでからのお楽しみという事で。
いやあ、韓国文学って(読書会でいただいたエッセイはありましたけど)恥ずかしながらこの小説が初めてなのです。ちょっと初めての文学体験って感じで、夢中になって読みました。翻訳の斎藤真理子さんの解説の通り、現代の韓国の姿が重なって見えてくる物語。シビアな緊張感が、とぼけたユーモアにくるまって、意表を突かれる角度から、胸を刺されるSFワールド。
そもそもこの本を手に取ったきっかけというのが、韓国の作家、ハン・ガン氏のノーベル文学賞受賞のニュースでした。あの報道があった翌日、地元の別府市立図書館に仕事帰りに直行。沖縄の読書会仲間から推薦のあった『別れを告げない』を借りようとしたところ、図書館の職員さん曰く「申し訳ありません。実は、こちらの図書館では、この作者の小説が一冊しか置いていない事が今朝判明しまして、只今貸出し中でございまして。『別れを告げない』になりますと大分県内の公立図書館では、県立図書館に一冊だけございますが、それも今貸出し中でございます」というわけで、結構な予約の行列に今並んでいるところ(汗)というか、やはりというか? 同じ日に同じ行動に出た図書館利用者さんが結構いたらしき事に笑ってしまいました。むしろ連帯感すら感じてしまいました(笑)
気のせいか、最近図書館の新着本で韓国文学が増えてるような気がします。(今まで目に入らなかっただけだろうか? )
その代わりと言っては失礼ですが、ハン・ガンさん、ぺ・ミョンフンさん両作の翻訳もされている斎藤真理子さんの『韓国文学の中心にあるもの』を借りて読んだところ、これがまた素晴らしく、文学を通して韓国の近現代史を深く読み解く内容で実に読み応えがありました。という経緯での、今回の『タワー』の選書に繋がった次第です。
『タワー』はしっかり、別府の図書館にも置いていた! カムサハムニダ♪
Posted by にいさん at 2024年12月03日 18:43
『獅子の見た夢』(別府市民劇場第125回例会)

別府市民劇場第125回例会で劇団東演『獅子の見た夢』を観ました。史実に関するところは触れますが、ネタバレ抑え目に。
彼岸と此岸とを対話させる術を、文学は持つ。
演劇もまた然り。
想像の産物と言われればそれまでだけれど。
三好十郎と彼ら「桜隊」「苦楽座」の再会を、確かに感じた。というか、その前の稽古場の場面以上に、彼らは熱気を帯びて、リアルに生きてそこに居た。
彼らを葬り去ったのは、アメリカが投下した原子爆弾。
核兵器だ。
1940年。戦争に突き進む軍国日本は多くの演劇人たちを検挙・投獄しました。「平和を求める言葉」「政権批判の言葉」「時局に相応しくない」「国家の提唱する道徳に反する」とにかく権力が気に食わないものは片っ端から。表現の自由どころか権力の目から見て気に入らないものは即命の危険に繋がる時代。(そこまでの危険は無いと思われるが、自ら権力に忖度し自主規制を行う者との対比をどうしても考えさせられてしまうわけで。それは私自身の姿も省みずにはいられない。普段の生活で。blogやSNSでどれだけ忖度せずに発信出来ているというのか? 他者を踏まない表現への配慮であるとか、過去の経験からの、悪質な人たちへの対策の工夫であるとか、それらの言葉遣いが、結果、力ある者への忖度に繋がったり、はっきりとものを言わぬ事に繋がらないようにと自分に言い聞かせつつ)
検挙を免れた劇団は戦争遂行を支援する為のものに限定されていくその中で、演劇人たちは知恵を使い続けていくのです。慰問公演の移動演劇連盟への強制加入という理不尽の中、「ふたつにひとつは好きな演目を演じて良い」という(但し、公演に際しては国家への忠誠を示す唱和だかなんだかをやらなければならないがという条件はあるらしいが、という)道を選ぶ事によって、彼らは三好十郎の『獅子』という演目を選びます。そう。僅かな隙間から活路を見いだそうとした。
『獅子』を演じることは、彼ら苦楽座(桜隊)にとっての抵抗なのです。
「家」制度の呪縛から自分を解き放つ主人公の姿に託して。彼女を見送る父親の獅子の姿にその思いを託して?
しかし、戦争は劇団のメンバーひとりひとりの人生にも影を落としていくのです。特高に監視されるベテラン団員が取った決断。母と租界に行くかここに残って芝居を続けるか。赤紙がきた団員。
「武勲を…」「いや、駄目だ。ここにいる我々は、それを言ってはいけない」
警戒警報で、また稽古は中断を余儀なくされる。
戦時下の演劇人の葛藤が実に生き生きと、まさに目の前の俳優たちの肉体を通して伝わる迫力が。そんな彼らの舞台を観た当時の人たちは、どんなふうに観たのだろう? 何を思ったのだろう? そんな事にも思いが広がりました。
残念ながら、時代が流れても、その痛みの記憶が薄れていく頃、権力者は再び似た過ちを繰り返すと教えられてきました。この桜隊の物語は、これからも繰り返し語られなければならない。演劇人の先輩たちはずっと続けてきたその姿をずっと見てきた。時には舞台の上から。時には制作の現場から。目の前の利益以上に大事なものと向き合っているという現実は、今の演劇の世界も変わらない。(但し、経済に無頓着で良いとは言わない。いつもギリギリだった。三好十郎は勝手な事を言うものだと、半分羨ましくもなりながら、正直思った)それがいつのまにか「演劇=ショービジネス」のような印象を持たれたり、「演劇人はメディアの擁護ばかり」等とSNSにあがるのは非常に不本意に感じています(し、ワイドショーに出てる人らが演劇界を代表してるわけじゃないから。演劇人の考え方は舞台を観て知って欲しい。そこでの批評ならばわかると言いたいところ。しかし生の演劇を観に来るお客さんは決して多いとは言えない。だからこそ、市民劇場の話題を発信しているところもあります)。戦前からずっと、演劇人は平和を訴え続けてきたし。戦争が奪っていったもの・ことについて語り続けてきたのです。それはこれからも、そうあって欲しいと願っています。
先日のノーベル平和賞に、日本被団協が選ばれた事の意味と共に、この『獅子の見た夢』上演の意義について、改めて考えさせられます。核兵器など存在してはならないし、戦争は起きてはいけない。断固として。
#FreePalaestine
#StopGazaGenocide
#ロシアはウクライナへの侵略をやめよ
Posted by にいさん at 2024年11月30日 12:05
『アンチソーシャル・ネットワーク』Netflixでこれも必見のドキュメンタリー映画

(Netflixのドキュメンタリー映画。特にネタバレ等は気にせずに書きます。割と、前の記事で話した内容とも重なる部分も感じました。2作続けてご覧になるというのも、より地獄味が増して迫ってくるものがあるかもしれません)
市民運動(を名乗るが、実際のところは市民運動の名に値しない者たち)が自ら力を求めた末路の姿が、現にこの国でも、嫌という程見せつけられている気が、否、気がするではなく、目に入ってきて仕方がないのでありまして。
例えばQアノン。極端な陰謀論に染まり暴走した挙句、現実の政治に対してとんでもない影響力を持ってしまった。議事堂での暴動では死者まで出して。犬笛を吹いたはずの奴はまた大統領の座に返り咲いたって?無茶苦茶だな。
こんな笑えない冗談の極みのような事がコツコツと「草の根」で積み上がっていったことに驚きと怖気が走るのです。排外主義とデマは相性抜群で? 真面目な事実の積み重ねや論理の構築よりも「刺激的な嘘」に飛びつき信じてしまう人たち。「人種差別はいけない」という言葉よりも「あの勢力は人の生き血を吸っている」などという荒唐無稽な話しに飛びつき信じる人たちが、現実の政治に影響を与えてしまったらどうなるか? 草の根の極右とフェイクとが合体したモンスターが国を超えて暴れ狂っているように思えてならないというのがまさに「今」なのでしょうか。
このドキュメンタリーでは「アノニマス」についても触れられていた。久しぶりにその名を聞いたな。
匿名で緩やかに繋がったハッカー集団が、カルト教団や自由を抑圧する各国政府へ攻撃を仕掛けるという! なんというか、匿名の「仕置屋稼業の連合体」という印象もありました。単純に肯定出来る話しではないが(仕置人と呼んでしまったからには、まあ、法で裁けぬ悪党を-ってな話しになりましょうか。毒を持って毒を制すという話しになりましょうか)元々中心になっていたメンバーは、自由に対する脅威へは敏感であったとしても、そもそも世直しの為に始めたわけではなく? ただ、発祥の地たる4ちゃんのあまりの荒廃ぶり及び危険な影響力は怪物化して、ハクティビズムからは距離を置いていた彼らも目をつぶっていられなくなってしまったと!? やばい彼らが危機感を抱かざるを得ない程に膨れ上がってしまったQアノンを含む陰謀論は今や世界に広まってしまった。
Qアノンの亜種みたいな連中はここ日本にも。誰かへの攻撃で炎上を起こして金にするような奴らが、パワハラまみれの権力者や結託する企業との利益共同体のようなものを構築し!? (残念ながら小説や映画の話しではなく)デマ情報や不自然な凍結がまかり通る中、選挙というものまでが影響を受けてしまったのだとしたら、それは本当に恐ろしき話しです。民主主義が破壊されていく様を今まさに目にしているのでしょうか。
もちろん、アノニマスになる事はないにせよ、恐くて仕方がないと思った人間が、ひとり、またひとりと声を上げていくしか無さそうですね。政治の話しはタブーだから〜、とか、こんな噂が流れてて〜みたいなフワッとしたネガティヴ情報とかとか。根拠不明なものをひとつひとつ潰していく地道な作業が必要なのかもしれませんね。
こうした問題を(不正な行為、排外主義、デマは絶対に駄目だという話しを)話題にしていく。し続けていく事を。だから? こんな映画も観るといいかもよ〜って、話しでした。
Posted by にいさん at 2024年11月24日 17:43
『FYRE』Netflix配信ドキュメンタリー映画凄いよ

映画『FYRE:夢に終わった史上最高のパーティー』をNetflixで視聴。ドキュメンタリーですが、思うところあり、ネタバレ抑え目の表現で感想を。
「これはまずい」と声を上げた部下がいた。
彼は、無視され。やがて外された。
SNSから流れてくる情報に多くの人が熱狂した。
懸念の声は、SNSの熱狂に掻き消された。
悲劇は起きた。
責任者に、反省は見えない。
Netflixでこれは観たいと思っていたドキュメンタリー。日本ではあまり知られていない事件なのかな。しかし、事柄の性質上? 敏感にならざるを得ないというか。イベントごとに関わる人には知らせたい話し。否、イベントを企画する側の人だけでなく、「乗っかる人たち」にも。
自分なんて(前職における)手打ち公演や主催公演から、個人的な趣味のオフ会まで。大きなイベントとはとても呼べないながらも、それでも数十人や時には数百人規模の人が集まるだけでも、相当神経擦り減らすし、体力もかかるもの。たとえ小さなイベントであっても「いい加減なこと」なんか絶対に出来ませんよ。例えば、注目を集める為には嘘でもいいから情報を派手に盛って伝えるとか。たとえ最初は本当にデカい夢を試みたとしても、きちんと問題を指摘する声を受け止めるどころか「なんとかしろ」と力でおさえつけたり、排除する等という対応を繰り返す。聞いて心地好い事だけを耳に入れる、等というリーダーが存在する組織は、必ず破綻します。大事故へと繋がっていく。
これは、遠くの異国の島のビーチで起きた悲劇と思うなかれです。このFYREフェスと同じ何かがこの国のあちこちで起きている気がしてならない。(全てが同じと言っているわけではない、が、場合によっては、このフェス以上の悲劇が起きかねないという懸念は持っています)「それは詐欺だ」「いや違う。広告の表現に問題があっただけだ」これによく似たやり取りを以前どこかで目にしたような。話しが違う、お金が払われない、観客が怒って暴動を、何故負債をこの人が負わされるのか、巨大な国家的事業なのに危険がいっぱい!? 国際的な平和の祭典のはずが疑惑がいっぱい。。。
責任者や富裕層は大体逃げ延び、反省は見えずに。場合によっては家は立ち退かされ、庶民は置いてけぼり。貧困層は更に広がり、参加しないお祭りの喧騒に汗水流して支払い続けた税金は吸い取られていく。あの祭りの景色とこちら側の世界との区別が段々曖昧になってしまう。これは妄想だけれども、どうしても区別が曖昧に、なっていく。
責任者は、懲りずにいるのか。
見放された島の人たちはどうなる?
ふざけんなって声をあげたら、
SNSでの誹謗中傷ですか?
権力者は力を持ち続ける。
悲劇はどこかで、また繰り返される。
Posted by にいさん at 2024年11月21日 21:56
「沖縄式読書会」今回で30回目の開催となりました!


ほぼ毎月、別府市で開催してまいりました「沖縄式読書会」も、今回で30回目を迎えることとなりました。これもひとえに、この読書会に参加して下さる皆様のお陰でございます。本当にありがとうございます! これからもより一層充実した時間になりますように励みたいと思っております。今後ともよろしくお願い致します。
そんな記念すべき30回目の読書会に集まったのは、こちらの本たちでした。
宮崎駿『風の谷のナウシカ』(あの傑作アニメのこれが原作漫画。1巻から7巻のBOXセット! 現実の未来を予見したようなそのストーリーもさることながら、とにかく宮崎駿さんの描いた1コマ1コマの画力が凄い。7巻あるその一冊ごとに付いているポスター? このイラストも素晴らしく、読書会参加者一同うっとり見入ってしまいました)
小川洋子『人質の朗読会」(まず、この小説の設定に驚きました。もしかしたら、今の我々自身の生活とそれを巡る周りの状況とを暗喩しているのでしょうか? そんな設定からはかけ離れたような、ひとりひとりの人生の不思議が語られていくその内容にも、惹きつけられます。絶望的な中にあっても、打ち消せない人の記憶の光のような )
雑誌『coyote』(一年に3度発行される雑誌『coyote』今回の特集は南極!? 85歳にして黒田征太郎さんは南極大陸へ。その手書きの文章とイラストもとても素敵です。まさに黒田さんでなければ辿り着けない境地が。そして池澤夏樹さんの台湾紀行も魅力に溢れたエッセイ。南極から台湾まで今号も読み応えありますね)
内田春菊『ファザーファッカー』(選者様曰く「口にするにもあまりに酷く、衝撃的な」少女時代から、筆者が家を出るまでを描いた自伝小説。こうした話しを、今も耳にします。暴力を振るう者と、止めない者と。加害者は常に力を持った存在であり。著者は紛れもないsurvivorです)
井上ひさし『井上ひさしの作文教室』(前々回の読書会でプレゼント本として手に入った一冊。なんと幸せな作文教室でしょうか。自分もひさし先生から教わりたかった。と思ってしまいたくなるも、もうそれは叶わないことが残念でなりません。言葉を綴る楽しさ、言葉の豊かさ奥深さを感じさせてもくれる一冊)
白石雅彦『ウルトラマンタロウの青春』(ウルトラマンNo.シックス! 白石雅彦さんのウルトラドキュメントシリーズも、このタロウで7作目(『「怪奇大作戦」の挑戦』含む)。まさに第二期ウルトラブームの集大成的な盛り上がりを見せた今作。私の幼少期の記憶にも鮮やかに刻まれたウルトラ6番目の弟の闘いの裏側を丹念に追っていきます)
そして今回30回目のプレゼント本はこちら!
赤瀬川原平『老人力』(老いの力とは? 忘れていく-ということによって活性化されるものがあるという考え方。そして、何か身に覚えのある現状、もの、ことに対して名前を付ける、ネーミングすることによって人生を面白くしていくという発想。そして、巻末にはなんと、著者についての貴重な新聞記事が貼られているというおまけ付き! )
野見山暁治『四百字のデッサン』(最近、101歳で天寿を全うされた著者は高名な画家です。こちらはその画家として生きた著者が出会ってきた人たちとの出会いや出来事を綴るエッセイ。絵描きさんだけあって? 人間観察が鋭いとのご指摘。そして御自身の気持ちを赤裸々に語る文章にも興味をそそられます)
井崎英典『コーヒーを楽しむ教科書』(コーヒーは奥深い! そして、美味しい。豆の焙煎の仕方から、器具の種類から、コーヒー豆のその豊富な種類と味のバリエーション。「コーヒーを極めたいと思ったことがあって」という選者様の思いが溢れるプレゼンでした)
堀内リエ・たからしげる『マハトマ・ガンディー/阿波根昌鴻』(今回の沖縄関連本はこの阿波根昌鴻さんの伝記を選ばせていただきました。子どもはもちろん、大人の人たちにも知って欲しい非暴力の人物伝シリーズ。ガンディーと並んでタイトルてなっている通り、阿波根さんは「沖縄のガンディー」と呼ばれる民衆のリーダー。で、実はここ別府市にも縁がありまして……と、そんな話しもさせていただきました)
2020年の12月から開催しております「沖縄式読書会」も(途中、コロナ禍での休止の期間を挟みまして)早いもので30回を数える事となり、来月の開催で丸4年となります。これからも、沖縄の「本もあい」の楽しさを大切に、ここ別府市で本を通した交流を続けていきたいと思っています。沖縄の本も沢山紹介して広めたいと思っています。今後とも「沖縄式読書会」をどうかよろしくお願いします!
Posted by にいさん at 2024年11月17日 22:10
映画『ルックバック』がAmazonプライム・ビデオで配信開始!

今回、具体的内容のヒントに関する事にいくつか触れるかもしれません。映画『ルックバック』がAmazonプライム・ビデオでも観られるようになりましたので、真っさらな状態からご覧になりたい方は、是非そちらをまずご覧になって欲しいです。
あの「事件」の下敷きは、おそらくは、あの身勝手かつ凶悪な、あの放火殺人事件ではないかと思いました。
身勝手な暴力が奪ったものとは、未来。そこで作り上げられるはずだったもの。笑顔と充実感。憧れの人と喜びを分かち合う瞬間。
それら全てを奪う権利など、誰にもない。
フィクションの力というものを、改めて感じないわけにはいかなかった。
フィクション、虚構、ファンタジー、というものは、誰か個人を、弱い立場に置かれた人たちを貶める為に使われて欲しくない。まして影響力ある作家が他者の人権を貶めるような言動など、目を耳を疑う衝撃が走ったその翌日に私はこの作品を観たことも忘れないでおく。
作中、藤野が言われた言葉たちのひとつひとつは、自分も何度となく投げ付けられてきたものだった。もう中学生なんだからそんなこと(怪獣、特撮、ヒーロー、アニメ、時には描いてもいたそれら全てを)卒業しなきゃ、受験があるんだから部活なんか(と他所のおばちゃんからは言われ)受験があるんだから旅行なんてしてる場合か(などと宣う先生もいらっしゃったが、あの佐渡での芸術祭典に関わっていた劇団に私はその後実際に入団することになる。私にとっては真面目な将来を見据えた祭典への出席だったけれども、あの時の中学教師にはそんなことより目の前の受験だったのだろう)などという「圧力」は、今思い返すと、まあまあ恐ろしいですよ。藤野を襲った「もう卒業しなきゃ圧力」というものは、全員が均質に歩調を合わせる社会を、従わせる者と従う者双方が、その意味を深く省みることもないままに作り上げ、はみ出す者は排除していくという大きな構造を作り上げてしまった。そこでの強者は概ね男性らしい。そいつが「全体の生産性」を語る時は、特に気をつけた方がいい。
フィクションの世界とは、本来、そうした「現実の力」に対して、抗うものではないのか? いわんや女性に対して暴力的な「自由の制限」を求めるなどと、作家を生業とする男性が現実の世界で(それも今2024年だよ? どれだけ時間が逆行しているというのか)公言する世の中に今私は生きているという悲しみに、この映画の物語はやけに沁み入ってきたようです。
「もし」を想像する先にあるものについて。それは、絶望であって欲しくはないし、弱い立場に置かれた人たちを貶めるものであって欲しくは、ないかな。
そして、いままた、あの事件を思い出しつつ。
鎮魂という言葉の意味についても改めて噛み締めながら。
Posted by にいさん at 2024年11月10日 13:02
ドラマ『団地のふたり』が身につまされてならなくて

先日最終回を迎えたNHKBSのドラマ『団地のふたり』の感想。基本的にネタバレ、というほどの大事件や衝撃的な展開、大どんでん返しのような事は起きないけれども、とりあえず、ネタバレは抑え目に。
この最終回を見る直前に『地面師たち』見てたんですよwもう、頭ん中わけわかんねー感覚で見終えた事も、多分一生忘れない。(地面師たちの活躍と紐付いてキョンキョンと小林聡美さんのドラマが記憶される事となるでしょう って、そんな話しはもうええでしょう。団地のふたりの話し、進めませんか!? ってピエール瀧さんが頭の中で言うてます)
舞台は団地。築半世紀を過ぎる、今では古い集合住宅。かつては文化的住宅とか言われた時代の、四角くて長い、大きな集合住宅が集まっている景色。そんな一見平凡な団地の風景だけど、よくよく見ると、緑があって、住民同士が笑顔で会話しあえる距離感で、憩いの空間もあり、互いの生活を感じられる心地好さ。そんな良い環境に思えるのだけれど、しかし住んでいる人たちは、今ではかなり高齢世代が多く、若い人たちの多くは団地から姿を消していっているらしい。主人公のノエチとなっちゃんはこの団地で生まれ育って「帰ってきた」幼馴染みの55歳。ノエチは両親との3人暮らし(うちと一緒だ)なっちゃんはお母様とは離れて暮らす一人暮らし。夕ご飯は大体なっちゃん家でなっちゃんの作った料理をふたりで食べる。休日のお昼はベランダでふたり優雅に? 喋って過ごしてたら、やたらとご近所さんから声をかけられるところとか、見ていてめっちゃ良いなって思います。
というこのドラマの設定そのものが胸にサクサク突き刺さってきてならないわけです。身につまされてならないというか。
ちなみに私の住んでいるのは、団地ではなく、築40年程の古くなってきたマンション住まいで微妙に違うにしても(まあ、階数が多少あってエレベーターはあるが、うちは低い階だしエレベーター使わないし)同じく「古い集合住宅に住む住人あるある」は、まんまうちも当て嵌まるわけで。団地の理事会とかも。(うちは、町内の自治会が月イチと、マンションの会合が年に一度位。最近、出席を親から引き継いだところ)
まず、これはノエチとなっちゃんにサクマのおばちゃんが言った台詞ではなかったか? 「この団地に若い人がいると良いわね〜」と言われて共に50代のふたりが苦笑いする場面。同じく50代の私が去年くらいにマンションのおっちゃんから言われた台詞はこれ。「このマンションにあんたみたいな若い人がおったんか! 」「いや、もう50過ぎてますんで(笑)」というやり取りを思い出して、ドラマ見ながらもう可笑しくて仕方がなかった。この会話が象徴するように、圧倒的に親世代の先輩たちが多いわけです。ノエチの両親も、ほぼうちの両親と同世代で。片方が体調悪くすると、もう片方が元気になる(しっかりしてパートナーを支えなければ。となる)というのも、うちも、まんま一緒です。序盤に登場した、仲村トオルさん演じるノエチが昔好きだった同級生の母親に対する眼差しは、あまりに深くえぐられる位共感してしまった。そうですよね。我々以上の世代は、親の老いとも向き合っていかなければならない。そんな切実さが詰まった団地の中で、でも魅力的に生きる人たちの交流が、こんな、平凡な生活の中にもこんな潤いが! こんな驚きの歴史が!? (ベンガルさんの活躍回は「神回」と呼んでいます。あれって、日本の団地の歴史ですよね。日本中に、ベンガルさんはいたんですよ。たぶん)
ただ、そんなノエチとなっちゃんに共感しつつも、大きな違いももちろんあります。そりゃそうだ。ふたりは、人間的な魅力のみならず、結構な「達人」なのであります。「できる人」なのでありまして。
ノエチはかつて神童と呼ばれた女の子。大学院まで進み博士号を取得して、エリートコースをまっしぐら、かと思いきや、(どうも女性差別の匂いさえする)大学内での政治的な理不尽により、ドラマスタート時は、非常勤講師という、本人の実力からすると不本意極まりない肩書きで。本人も何度も「非常勤講師だ」って、そう言っているにも関わらず、団地のおばちゃんたちからは「のえちゃんは大学の教授」と認識されてしまっている。そんな中でも、仕事はしっかり真面目にやり抜いているノエチ。
かたや、なっちゃんは絵の才能有り。優れたイラストレーターで。以前は「売れっ子」だった時代を経て、今ではイラストだけでは難しいらしく、昭和レトロなお宝をフリマで売って、高く売れた時には、料理がちょっと贅沢になるという具合。とにかくドラマの魅力のひとつでもあります、なっちゃんの作る料理が美味しそうで美味しそうでたまらない。料理の腕前が素人のレベルではない。(小林聡美さん、実際料理お上手そう。『かもめ食堂』を思い出しましたよ)
このふたりがいるだけで、団地の調和が保たれているような? (あと、いつも不機嫌なベンガルさんも実は団地を見守り続けていた)皆から頼りにされまくって大変そうというか迷惑千万というか(笑)しかし、幸せな光景に見えてならなくて、真実癒されてしまいました。
団地内の(空ちゃんとの思い出の)保育園も閉園したり、子どもたちの姿が減っていくのは寂しいけれども、新たにやってきた若い家族が、その子どもたちのドラマにも救いがありましたね〜。最終回のあの動画の展開も良かったな〜。
このような景色が、これからも、この国から無くなりませんように。
それから、最後の「新年の目標」だっけ。いっこ足りなくないですか?
そこは、もうひとつ。
ドラマ『団地のふたり』season2を放送する!
って言って欲しかったな〜ヽ(´▽`)/また、ふたりと、団地のみんなに会いたいです。
Posted by にいさん at 2024年11月06日 21:18
Netflixで『地面師たち』

先日、視聴頻度の低いサブスクリプションを整理して、新たにNetflixを契約したのは、このドラマを見るのが目的でした。
『地面師たち』
2017年に実際に起きた地面師たちによる巨額詐欺事件をモデルとするドラマ。55億5千万円もの金額を、超有名な大手ハウスメーカーが騙し取られるという、前代未聞の大事件。実際の事件では、品川の老舗旅館だった土地が舞台となり、かなり地元では有名な場所だったそうですね。私は13年東京で暮らしましたが、品川区五反田なんて、一度も足を運んだ事がなかった気がします。仕事で五反田の小学校あたりに行った際に、もしかしたら、すぐそばを車で通ったりしたのだろうか。なんて事を思いながら見ていましたが、ドラマでは港区高輪に場所を移して、舞台は旅館ではなく……
その内容は、ドラマをご覧になってください。この土地の購入代金についても。
地面師とは。土地の所有者になりすまし売却をもちかけて、多額のお金を騙し取る不動産詐欺。こんなハリウッドのコンゲーム映画じみた行為が、この日本で、それも2017年に実際に起きた事には驚かされます。そういやそんなニュースもあったっけ、って感じでしたが、改めてドラマとして描かれると、その犯罪集団だけではなくて、この舞台になった業界だけに留まらない、深刻な問題を孕んでいるように、等とつい思ってしまう。
何故そこまでして「土地」なるものを欲しがるのか。いや、土地そのものよりも、その土地が生み出す利益に執着する人間たち。このような世界と縁の薄い庶民からすると、正直ちょっと正気とは思えないのです。その土地が持つ(真実、価値を持つと思われる)環境資源は無惨に壊されて、タワマンや商業施設が建てられるだなんて、自然にとっては負荷でしか無いわけで。一体どれだけのエネルギーを消費するというのか。むしろ汚す行為でしか無いわけであって。その開発をズカズカ行って(結局一部の富裕層が)儲ける行為を正当化することが、私にはどうしても出来ません。
ハリソンが語った通りですよ。そもそも「土地」というものは、太古の昔から、我々人間が生まれるずっと前から「そこに在る」物であって、後からそこへ住み着いた人間たちが自分たちの都合でそこを所有した上、値段(価値)なるものを付けて、価値を釣り上げ儲けをあげて。その土地の価値を巡って狂乱を繰り広げる光景など、そもそも、なんなのか? と醒めた目線でつい見てしまうのですが。
(トヨエツ)ハリソン山中はそれを見ていた。醒めた目線で? 否、違うな、冷酷な視線だ。これ以上なく、底知れぬ恐ろしさを持った。
餌食になるのはマチズモの塊のような者たち。笑顔の裏側の欲望、野心が次々と狩られていく様に、その恐怖に歪む顔に興奮を覚える冷酷な男。強欲な資本主義の塊みたいな連中が狩られていく。こういう事が現実で起きているというのか。必死で競争社会を勝ち抜いて、ライフハックして、ドヤって、古くなって、油ぎった昭和臭まみれの塊が、ひとり、またひとり消えていく。小さな悪がより大きな悪に喰われていく地獄絵図。
一度その沼に嵌ったら最後、抜け出せないのか綾野剛、否、辻本拓海よ。よりによってハリソンの沼に嵌ってしまった、その地獄の顛末や如何に。
というわけで、Netflixという沼は、危険な場所だったようです。
Posted by にいさん at 2024年11月04日 20:24
Netflixの沼に嵌る

サブスクリプションって、加入する時は割と親切設計で登録出来て、尚且つ初回の無料キャンペーン期間なんかで(WOWOWはそれで加入したんだけど)楽に始められたのに、いざ解約するとなると、
手続きが複雑でわかりにくい
この手続き。デジタルに弱い自分には、難解過ぎだな(汗)
というわけで、困った時の久しぶりのauショップさんで相談して、解約の操作を手伝ってもらいました。ありがとうございましたm(._.)m
「わかります。解約手続きって面倒なんですよね〜」
そうなのですよ〜(泣)
一度嵌ったら簡単には抜けられない。そんな罠(配信サービス)がひとつ増え、またひとつ(恐)
てな具合で加入してきたサブスクリプションサービスという罠。次第に、加入当初ほどには利用しないサブスクも出てきたもので。毎月の支払いの方が高くつくというパターン。メインだったAmazonプライム・ビデオは安定して(しかも安い! )良作を提供してくれるのは有り難しで手離せないけれど、テラサは(ほぼ「相棒」シリーズ過去作専用サブスクと化していたのが)利用頻度が減っていき、久しぶりにログインしようとしたらパスワードが覚えてたのと違う? なら、いいや。そしてWOWOWオンデマンドは見応えのあるオリジナルドラマやLIVE配信も捨て難いのでありますが(ドラマW『フェンス』を見られただけでも入った価値はあったけれども)月額料金が高い。世の低所得層にはきつい。月に何度かは見るが、段々利用料金に見合わなくなってしまった……というわけで、テラサとWOWOWオンデマンドよ、今までありがとう(涙)と、さよならをしてきました。
WOWOWはな〜、時々良い出会いがあるから迷ったのだけど。ライムスターのLIVE配信してくれてありがとう。
そして新たに加入したのが、長らく、料金的に迷っていたあそこ。
にいさんは、いつNetflix始めるんですか?
と、言われて何年経っただろうか。最近、790円の広告付きプランが出来て、それならそろそろ、と思ったところでWOWOWで『フェンス』というドラマが始まっちゃって。追い討ちの如く「ひと月無料キャンペーン」でそっちにいっちゃったんですよね〜。『フェンス』がとにかく素晴らしいドラマで、キャンペーン期間過ぎてもせっかくだからと続けてきましたが、他のオリジナルコンテンツの期待作が、個人的な好みとしては若干合わなかったかな。『フェンス』を見た後だから尚更?という次第で、遅ればせながら、ならば、利用の少ない配信は整理して、いよいよサブスク界の頂点に-という感じでしょうか。
今も利用してるAmazonプライムももちろん良いのだけれど、更にエグ味のある題材を、しかも映像が、これ、日本のドラマのクオリティじゃなくね? っていうこのドラマ。最初の10分で持ってくな〜。言葉遣いの丁寧なトヨエツ恐ぇよ。背筋が凍るよ。綾野剛の好演も魅力的で……
更にこっちの映画は、新宿駅で、え、掲示板なんて今どき無いだろ? ん? 画面がスライドしていく、掲示板にチョークで書かれた文字が浮かぶ。
NETFLIX
新宿って街は、今でも恐いところですよね。
Posted by にいさん at 2024年11月03日 17:36
『しんぶん赤旗』購読者が周りで急増中(驚)

1週間が経ちますが、選挙戦お疲れ様でした。党派を超えて、思想信条、好きな人も嫌いな人も、皆んな皆んな、本当にお疲れ様でした!
選挙って、エネルギー使いますもんね。もう、これだけは言える。立場を抜きで、そこだけは、労いの言葉を送らせて下さい。
しかし、こんな選挙は初めてでした。
投票権を得て30年ちょっと経つけれど、こんな経験は初めてかもしれません。応援していた政党が議席を減らしたのにも関わらず、周りの人たちから、或いは他党の支持者の皆さんからまでもめっちゃ評価や賛辞の声が(私個人にまで)集まって。極め付けは、政党機関紙「しんぶん赤旗」の購読申し込みが殺到しているという話し。選挙後2日で1000人超えて、今もなお増え続けてるって話し。
沖縄の友人も、別府市内の身近な方も(党本部経由で申し込みが)目に見えるところで購読者が続々と増えてるなんて事、今まで一度もありませんでしたよ。大体、ボランティア仲間以外で赤旗取ってる人なんて会った記憶がありません。しまいにゃ(昔、東京・世田谷区のアパートで)うちに来たNHKの口の達者な集金人のあんちゃんから「え、今どき赤旗なんて取ってる人がいるんですね」なんて失礼な台詞まで思い出しちゃいましたよ。
今回の選挙、とにかく、自公の過半数割れは本当に良かった。決め手は赤旗の裏金スクープだったとよく言われていますが(もちろん、上脇教授の力も非常に大きなものがありました! )自民党の議員が「赤旗裏金バズーカにやられた」、立憲民主党の幹部のひとりは「MVPは間違いなく御党と『しんぶん赤旗』だ」「裏金スクープから最後の非公認候補への2000万円の支出に至る一連の『赤旗』報道がなければ、今回の選挙も与党過半数割れもなかった」とまで言ってくれるとは。某連合の会長が例の如く「共産党と連携しなくても選挙に勝てる」等と豪語したのに対して、最大の支持団体かもしれないその代表の発言に対して立憲民主の議員さんから断固とした批判の投稿があがったのも印象的でした。(石垣議員ありがとう)大手紙でも朝日、読売だけじゃなく、あの産経新聞までもが「2千万円を支給した問題が報道され火に油を注いだ」と報じる始末。(連合のやり取り以外、コメントは10月29日の赤旗より)
何故、大手紙は報じられなかったのか? 裏金とか、政党助成金の交付先の話題とか、報じ難い、手を出し難い何かがあるんですかね? まあ、後追いでなら記事に出来るっぽい事はわかったけれど。単純に赤旗を持ち上げたいわけじゃなくて。最近のスクープが(全てとは言わない)ほとんど赤旗と文春が持っていってない? っていう現実は、シビアに受け止めています。赤旗が抜きん出ているふうに見えてしまうというメディアの現実がやばくないですかね。赤旗が増えるのは嬉しいけれど。(与党の政治家から情報「もらって」たら無理か。仲良しこよしやってたら無理なのか)
選挙直後に #ありがとうしんぶん赤旗 ってハッシュタグが拡散されてるのを見て、ちょっと感動してしまいましたね。
又、一方で、
MVPより票をくれ
っていうのも正直なところ……
しかし感情に浸っている暇はないぞ、という気持ちでいます。選挙は終わったら全て終わりじゃなくて、むしろこれがスタートなんです。国会はこれから始まっていくんですよ。今、キャスティングボートを握る「ハメになった」らしい国民民主党なる政党の党首のひと言ひと言に国民がざわついていますが、よく見ておきましょう(予定してたより、ちょっと多く取っちゃった、ってびびってる? 気のせいか)選挙中に明言していたことをこの人たちは守るのかどうか。むしろ選ばれた後にこそ真価が問われることになるのですから。
身近では共産党と自民党に肩を並べる位に支持者の目立つれいわさんの差別動画も、ちょっと深刻に受け止めています。太郎くんには以前、沖縄での出会い以来好意を持っていたし、道は違えど最後は同じ(近いというべきか? )ゴールを目指していると信じたかったが、先日のおおいしさんの釈明文には言葉を失いました。本当に、悲しくなってしまった。
選挙中も、racism丸出しの政党、候補者が目立ったように感じました。まさかの政党が議席を確保する事態も。(但し、所謂極右と見られる政党と自公合わせても改憲は無理、という勢力図になった事は素直に嬉しい。が、油断は出来ませんね)これが、いまのこの国の景色なのか。という思いでいっぱいです。
そんな思いも抱きながら、改めて、しんぶん赤旗、私も購読しています。って話しになります。日刊紙が月3497円。日曜版が月990円。電子版のお試し購読はなんと、お試し期間が過ぎたら自動更新じゃなくて「自動解約」だそうですよ。良心的過ぎだろ!? 周りでは「電子版のお試しから」とか、「日曜版からとり始めました」という声が聞こえてきますね。文字通り与党を大敗させた「赤旗砲」のスクープはもちろん、私は文化欄が充実しているところも気に入っています。話題の人たちのインタビューもスキャンダラスな事を聞かないのが良いって言われています。ちなみに日曜版今週のインタビューは『虎に翼』の山田よね役・土居志央梨さん。舞台やエンタメの話題、本の話題がスポーツ欄よりも充実しているw(正直に突っ込むとプロ野球ファンには不満な紙面ではないか? と思いながら読んでいる)エッセイ好きな人、常盤貴子ファンにもお勧めしたい(常盤さんのエッセイかなり良いっす)。そして大好き『まんまる団地』の四コマに、いつも癒され、笑顔になっています。
笑顔にはとてもなれない世の中だから。是非あなたも、赤旗仲間になってくれたら、私も嬉しいです。
Posted by にいさん at 2024年11月02日 23:02
#比例は日本共産党 のこころ。(実は期日前投票済ませてた)

(10月26日に記す)
実は、ちょっと前に、母が緊急搬送されまして。久しぶりにヒヤッとさせられました。良くない発作がきて、緊急処置の後、丸1日、呼吸の苦しさを訴えられて。一番苦しいのは本人ですけれど、代わってやれない家族の歯痒さがありました。生きた心地のしなかったあの日。救急車で病院に送り届けた後、面会は14時から17時の間で15分だけ(家族ひとり)という事で、この15分の面会に1日分の集中力を注ぐような気持ちで、ここ数日を過ごしてきました。
それでも(面会+病院までの往復等で約1時間分増えたような1日が)時間は進んでいきます。今はやっと、母も回復しつつありという事もあるのか(明日は日曜日で面会は出来ない日という事とか)少し脱力というか、体はそれなりに疲れていたらしく、これまでを振り返るひと時が今、出来たかなってな具合てございます。
という、そんな日々の最中に、行ってきましたよ衆議院選挙の期日前投票。
母の入院費の事等まさに今支払いのことも話し合ってきたところなのですが、普段より、両親共に少ない年金生活の中で医療費が馬鹿にならない。大体、なんで親が後期高齢者なんて呼ばれなきゃならないのか(怒)と、例の医療制度が持ち上がった際にも腹が立って仕方なかったわけですが、言葉ひとつ、負担額ひとつが家族にとっては突き刺さってくるわけですよ。その一方で与党の政治家さん裏金でしょう? 冗談じゃないよ! ってな思いも益々募ってくるわけであります。
そんな激しい怒りをこめて、
比例代表は日本共産党
選挙区(大分3区)は大塚みつよし
と書いて投票してきました。
自民党の裏金を暴いたのは上脇教授としんぶん赤旗のスクープ。そして共産党議員団の追及あったればこそです。比例票は死に票にならず議席数に反映します。日本共産党の比例票が増える事で今の政治を少しでも良くしたい。切実な願いを込めて。(この裏金問題を連呼しながら立憲が票を集めそうだって話しがどうしても納得いかないんですよね〜 ってな思いも込めて)
3区といえば自民党の岩屋毅。彼は防衛相時代に、沖縄での県民投票の結果を受けて「沖縄には沖縄の民主主義があるのかもしれないが、日本には日本の民主主義がある」という意味が謎過ぎな暴言を吐いて県民を激怒させた男。更には辺野古への資材搬入に関わって、本部港が船を出さないなるデマも口にした事、忘れていません。岩屋氏への批判の1票を大塚さんに。
いや、今、与党自民党と公明党だけじゃなくて、野党を名乗る政党もなかなかやばい発言がわんさか出てきて怖気がたって仕方がないのでありますよ。若者支援の文脈で高齢者よりも若者への支援を-という話しじゃ済まずになんと「尊厳死」というワードが玉木なる議員から出された事には驚愕するやら恐ろしいやら。高齢者と若者の分断に繋がりかねない論調自体も大問題だと思っていたら、選べないような状況を作らされて、福祉も削られて、尊厳ある最期を-との実施国での地獄のような事例を知らないのか? 党首クラスでこのような言葉が飛び出す今の日本まじでやばいだろ。
ギリギリ野党と呼んでいた立憲民主さんは野田さんがまさかの党首選で勝利し、もはやギリギリでもなくなってしまった、という思い。あれだけ皆で必死になって反対の声をあげた安保法制を容認!? 原発も容認!? そして沖縄に対する態度は沖縄県民だった頃にあの人が首相であった頃の振る舞いを思い出さずにはおれない。
それから、周りでは「共産党か社民かれいわかで迷ってるんだよね〜」という声がよく聞かれるんですけどね〜、山本太郎くん、ちょっと個人的には、遂に信用が消滅したというか。先日の沖縄1区を(あたかも、じゃなくて「もしあそこで降ろしてもらえたら、1区を降ろしますよ」って)取り引き材料としてあけすけに語った言動に心底怒りでいっぱいだったところで、更に振る舞いがエスカレートの今朝のあの差別的動画で言葉を失ってしまいました。
これまで、れいわは支持者の一部の人たち? の暴走とか、大西事件とか(これも、命に関わる事だった)現場からどんどん人が去っていく話しとかは耳にしていたけれども、あの沖縄でお会いした山本太郎くんという人間は、正直嫌いにはなりたくはなかった。本当に今朝は、残念だった。悲しかったです。
そんな、政治の世界の恐ろしい景色と、私の生活での現実の厳しさ。何より、母が元気になって平穏に安心して家族で暮らせる世の中(私にとってのもうひとつの地元・沖縄での辺野古新基地建設断固阻止を実現させる! という前提の基に)より良い世の中を願う期日前投票でした。
追記。先日の、自民党が非公認のはずの裏金候補側へ政党助成金から2000万円を振り込んだという赤旗のスクープにも驚きましたね。(一体誰を助成してるんだか。それ、私たちの払った税金ですよね)記者からこの赤旗スクープについて問われた石破首相「報道の仕方に憤り」を感じるって? そんな答えを返してくる石破さん、あなたに憤っておりますよ。核保有論者の石破さん。
Posted by にいさん at 2024年10月26日 21:16
映画『私は憎まない』憎しみの連鎖を断つために

むしろ内容を伏せることなく書かねばならないと思います。しかし、まず是非ともご覧になっていただきたい。今、別府市のブルーバード劇場で上映しています。あなたも是非とも、足を運んでほしい。傍観者である以前に、この虐殺に無関心で済まさぬ為に。
パレスチナとイスラエルの架け橋になるという理想を医師は持った。医師はガザの男性。四方を完全に封鎖されたガザ地区の国境のゲート、本当に見てるだけで恐ろしい。何人がパスして通過出来るのだろうか。こんなに人間が狭い場所でひしめいている光景にも衝撃を受けます。ジャーナリストも通過の為にひと苦労。すると、ひとりの男性だけは、普通にゲートを抜けていく。この男性こそが、本作の主人公、アブラエーシュ医師。
「ユダヤ教徒、イスラム教徒、キリスト教徒の赤ちゃんの違いは? みんな同じく生まれたての赤ちゃんだ」
人の命への眼差しに迷いがない彼は、地元ガザの人たちのみならずイスラエルの人たちからも尊敬を集める産婦人科医です。
その彼の家族に悲劇が襲います。2009年、イスラエルの戦車が自宅の間近から(言うまでもなく軍事施設などではない、どう見ても民間人の普通の住宅です)砲撃をされ、娘3人と姪っ子とが目の前で殺されてしまうという虐殺に遭うのです。目の前で。そしてその現場から直電を受けて番組本番中のイスラエルのニュースキャスターが、その彼の慟哭を番組を通して発信するという衝撃的場面を世界中の人たちが目撃することになりました。(私は恥ずかしながらこのエピソードを知りませんでした)偶然放送を見ていたという当時のイスラエル首相はただちに軍に攻撃を(一旦ですが)やめさせます。今の首相は、それさえも出来ないようですが。
映画のタイトルは『私は憎まない』。それは確かに彼が言ったことではあるし、それでもカメラの前で彼はイスラエルの人たちへ向けて「共存」を訴えたのもその通りです。しかし、誤解してはいけない。それは、過去の悲劇を無かった事にするとか、水に流すとか、憎まないから握手しましょうなんて事じゃない。むしろ、激しい怒りに震えながら、イスラエルの罪を法に問う、裁判に打って出るのです。作中何人もの人たちが「イスラエルの司法は信用出来ない」と言い。又、無法な虐殺を行った軍は決して非を認めようとはしない。同じイスラエル人でさえもが唖然とする程に、頑なに。何度も何度もイスラエルの罪を訴えては棄却され。軍の見解は「問題の無い戦闘行為であった」と、ちょっと聞いてるだけでも苦しくなってくる展開。
これは、暴力の二次加害ではないのか?
まるで、彼の家族が、繰り返し殺されているような。
「傍観する世界への失望」を彼は口にする。その言葉のひとつひとつがスクリーンからこちらに刺さってくる。この痛みから避けるように? 多くの人たちは目を背けているということか。
今、更に残虐さを増した殺戮がガザを襲っている。メディアの中にはこれを「イスラエル対ハマス」などとまるでパレスチナとイスラエルとが同格であるかのような対立構図で表現する行為を私は憎む。一方的に占領し支配し、圧倒的な力関係のある者がジェノサイドを行う犯罪を、対等な戦争であるかの如く描くのはやめろ。と思わないわけにはいかない。
そこには多くの「同じような家族」がいたことを、この作品を観た後では、想像しないわけにはいかない。
そして、たとえ何度「イスラエルの司法」に跳ね返されようとも、
そのあげた声は残る。
彼のあげた声に寄り添う存在は、たしかに在る。むしろそれは、少数派ではないぞ。
国際司法裁判所は5月24日、南アフリカ共和国がイスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区南部ラファでの軍事作戦停止を要請した件を受けて、イスラエルに対し「ガザ地区での軍事作戦を停止するよう暫定的な措置」を命じました。
さらに、国際刑事裁判所は、イスラエルのネタニヤフ首相らとハマスの指導者に逮捕状を請求。
なおもイスラエルを支援するような動きもはらむ中、それでも世界中の人々の声は広がり、国際社会による世論の包囲は強まっているように見えます。パレスチナへの連帯。イスラエルへの抗議が地球を覆っている。世界はもう、それを目撃してしまったのです。
Posted by にいさん at 2024年10月21日 20:41
「第29回沖縄式読書会」開催しました!


別府市で(ほぼ)毎月開催しております沖縄式読書会も、いよいよもうすぐ30回を迎えようかというところまでまいりました! そんな昨日(10月20日)は第29回目。初参加の方2人を含む定員いっぱいの6人の参加で行われました。会場はいつものyoiyaさんで。しかし嬉しい誤算と言いますか、盛り上がり、話しは膨らみ、時間も2時間オーバー(汗)でも楽しかったですね。初めての顔触れもあり新鮮な対話が弾みました♪
そんな今回御紹介のタイトルはこちら。
『山之口貘 詩集』
沖縄タイムス『アルバム 山之口貘』
茨木のり子『貘さんがいく』(沖縄を代表する詩人・山之口貘に関する3冊ですが、まさかまさかの写真アルバム!?という意外な角度から〈しかもなかなか美男子な貘さんにもびっくりしつつ〉茨木のり子さんが貘さんについて書いてある一冊とか、あるのですね。そして何よりも、山之口貘の詩の魅力を存分に語っていただきながら、彼の生き様までもが生き生きと伝わってきました。「生活の柄」についての話題も熱く)
『忌野清志郎 総特集』
忌野清志郎『瀕死の双六問屋』(山之口貘の次は忌野清志郎しばりで! このようなユニークな「しばり並び」は初めての展開かも?? 総特集は清志郎さんの魅力をたっぷりに詰め込んだMook本。『双六問屋』はなんと清志郎さんが書いたファンタジックな設定でのエッセイ!? 「架空の心の拠り所」より愛する誰かに向けて書かれたメッセージ。それはまるで清志郎さんの歌の世界そのもののような?忌野清志郎は、今も多くの人の胸の奥に、生きているのですね)
木村セツ『90歳 セツの新聞ちぎり絵』
木村セツ『94歳 セツの新聞ちぎり絵日記』(90歳を迎えてちぎり絵作家になったという著者! 高齢の親持つ身としても、このような、セツさんのような存在こそが救いなのでありまして。今回、初参加のメンバー様が御紹介下さいました。この、新聞紙を使ったちぎり絵が、実に精巧で、良く作り込まれていて感動させられます。続編の94歳の『ちぎり絵日記』では、更に進化・深化しているような!? よく見るとわかる新聞紙の質感と活字が見えているところも。こんなに素敵なアーティストがいるなんて、目から鱗の一冊)
墨佳遼『蝉法師』(遂に待っていましたこの展開!? 過去にこの読書会では、音声デバイスは何度か登場してきましたが、もしかしたらここでは電子書籍は意外と初めてかも!? Kindleで御紹介のコミック。この作品は知りませんでした。蝉を擬人化? それも「法師」? ツクツクで、法師? 地上に出れば消えると知ってのこの命。唱えて歩こう命咲かせる我らが人生。否、蝉生。彼らは命の限りに唱えて歩き、恋に生きる? もうひとりの初参加メンバー様が、読書会に新しい風を運んで下さいました。なにか、夏が帰ってきたような)
保坂隆『お金をかけない老後の楽しみ方』(老後をゆるっと楽しく。地域で主催される生涯学習の集まりには積極的に参加すること。お金をかけなくとも趣味を持つことで豊かな時間を手に入れる。しかし「健康」にはお金をかけると著者は訴えます。いま、特に定年退職をした男性が陥る老後の「これから何をやって生きていけばよいのか問題」が深刻であると聞きます。老後にかかるお金がいくら、なんて話しも最近話題になりましたね。そんな心配を抱く人たちに読んで欲しい一冊)
写真には写っておりませんが、↑この本を御紹介下さったメンバー様が、この度「放送大学」に入学されたとの事(素晴らしい! )そこで上の一冊とも関連して、これからの人生を見据えての放送大学で学び始めた話しもしていただきまして『心理と教育へのいざない』『問題解決の進め方』という二冊の教科書を御紹介いただきました。
斎藤真理子『韓国文学の中心にあるもの』
写真アルバム『別府市の100年』(主催者からはこちらの二冊を御紹介。斎藤真理子さんといえば、先日ノーベル文学賞を受賞したハン・ガンさんの小説の翻訳者としても知られる話題の著者。翻訳以外での日本語の単著はこの本が初めてとか。韓国文学の歴史をまさに韓国という国の歴史と絡めて読み解く読み応え抜群の一冊。別府市立図書館で借りてまいりました。
『別府市の100年』は今年がまさに別府市政100周年という事で出版された、別府市民の間では話題沸騰中? 記念のアルバムです。別府タワー建設風景、別府大仏、路面電車、昔の、私の生まれる前の故郷の景色がもう、たまりません
 )
)そんな、新しいメンバーさんも加わっての今回の沖縄式読書会。プレゼント本はこちらのタイトル。
Emi『今日から変わる わたしの24時間』(タイパに疲れた人たちへ? 1週間、何をするのかを決める。子どもには時間の管理を自分自身でさせてみる。スマホと手帳の併用をうまくやる事で効率良く? 時間に追われる事なく、自分の時間を「ごきげんに過ごす」ことが大切なのだそうです)
上原栄子『辻の華』(沖縄ではかつて、女性だけで運営された「辻」があり、大和の花街とはまるで仕組みが違っていたそうです。そこで生まれたお座敷芸の世界。この場所でジュリとして育った著者自身の数奇な運命と、沖縄の戦中戦後の歴史について。まさに知られざる歴史の一面で、当事者として生き抜いた著者による貴重な証言でもあります。沖縄に造詣が深く、三線奏者でもいらっしゃる初参加のメンバー様が御紹介いただきました)
『もっとすごい! 10分間ミステリー』(「ちょっとした待ち時間でも10分で読めちゃいます」との話しで、この読書会に向かう際のバスの待ち時間でも1つのエピソードを読んでこられたとの事です。多彩な作家陣が腕によりをかけて仕掛ける10分間のミステリー。とくと御堪能あれ! )
川端康成『山の音』(川端康成の人に向ける観察の眼差しは鋭い。ここでは息子の「お嫁さん」に対する義父の目線が、この描写から浮かび上がるこの感情って、もしや……! 淡々と静かな描写の作品なれどもとても気になる御紹介の仕方(笑)更には出版年における巻末の解説の違いについての話しも面白かったです。是非、「解説」の読み比べもしてみたくなりました)
『沖縄 おとな旅プレミアム』
宇都宮徹壱『股旅フットボール』(『沖縄おとな旅…』はその名の通り沖縄のガイドブック。今から7年程前のガイド本という事で、このコロナ禍の間に、もう見られなくなってしまった景色もちらほら。
『股旅…』は今のJ3の前身? Jリーグ発足当初の3部リーグでプレーする選手たちの姿。サッカー好きにはこれはちょっとした歴史の証言的側面も伺える一冊かもしれませんね)
宮里千里『ウーマク!』(今回、主催者としてはとても悩ましいプレゼントの選書でした。この傑作エッセイにして沖縄のブックカフェから取り寄せた希少な一冊。手放したくない! という思いと、でも読んで欲しい! という思いとがぶつかって(笑)やはりここは、この読書会の姿勢としては「読んで欲しい」という選択をとりたした。著者の子ども時代の沖縄について。戦果アギヤーのこと。瀬長亀次郎が与儀公園で演説会を行ったエピソードについて。このような話しをこの読書会で共有する機会を与えてくれたこの本にも、感謝です)
Posted by にいさん at 2024年10月20日 22:43
映画『あんのこと』をAmazonプライム・ビデオで

(劇場公開時に見逃していた入江悠監督の映画『あんのこと』を観ました。ネタバレは抑え目に書きますが、真っさらな状態からご覧になりたい人は、今、配信でも視聴出来るようになりましたので、是非ご覧になってから読んで下さると嬉しいです)
彼女の頭上を飛ぶあれは何だ?
真っ青な空に真っ白い筋を残しながら飛ぶあれは、文字通り物理的なホワイトウォッシング。
コロナ禍を頑張る医療従事者の皆様を応援しています。
巨額の税金をかけて、当時の安倍政権下でおこなわれたそれは、主人公を助けてはくれない。彼女の身の上に対して、何の力にもなってはくれない。どころか彼女がやっと手にした仕事を奪った緊急事態宣言。その生活の補償に一体どれだけの負担がかかると?あのブルーインパルスなるものを飛ばす以上の負担がかかるのですか?過酷な思いを乗り越えて掴み取った環境が、少しずつ少しずつ崩されていく。そしてまた毒親の影が。守ってくれたあの人も、あの人も、え?ちょっと、何やってるの?
そんな地上の地獄を、空飛ぶホワイトウォッシングが塗りつぶしていくかの如く、飛行機が飛んでいくのを見つめる杏の姿が、とても印象的でした。
杏を救ってくれようとした型破りな刑事。この物語は、実際に起きた実話を基にしているというけれど、佐藤二郎さん演じるあのキャラクターはモデルがいたりするのか?かなり破天荒だぞ?という彼の個性はともかく「あの人のような力を持った存在」はよくよく目を凝らして見るにリアルに感じられて仕方がなかった。ひとつの解釈として、きっと彼自身の真ん中には「彼の正義」はあるのだとして。サルベージを無くしてはならないという思いは一応嘘ではないとは受け止めたとして(サルベージとは引き揚げる、救い出す、救出するの意味)が、しかし、どうしようもなく弱いというか、己の「力」に溺れてしまったというか。杏の前進を喜ぶ裏であんた‥…っていう。こんな人、こんな組織、関係性って、まあまあ存在してる気がしてて。仮に始まりは善意だったとしてもトップが力を持ち過ぎると、どこかで破綻を来たすというか、閾値を超えてしまう危険について、最近も常々考えていたところ。大なり小なり「力」を持つ人間の振る舞いというのは、周りの人間の人生にも影響を与えかねないんですよ。場合によっては命にも関わるのです。組織であれば、先生ひとりのカリスマ性なりに依って立つ構造というのは、問題を感じてしまうな〜。
それも、これも、本来ならば「公」がフォローしてしかるべきところを「自助か共助でやれ」って言うんだから地獄ですよね。直接的にはあの毒親への怒りももちろん激しく湧いてくるのだけれど、よくよく見るとこれは「この環境を作ってしまった外側の世界」にどうしても目線が向かうような作りに思えてなりませんでした。この日本には、確かに杏が生活していたのだと真に迫ってくるリアリティを感じつつ。
とてもショッキングな話しだし、主人公に近い境遇の当事者の方や、同様の体験をされた方へ気軽に観て欲しいとは言えません。(又、私はどうしても、男性目線で大変な境遇の女性を描くという事の難しさも感じました。欲を言うと、当事者自身の言葉や意志が更に強く描き出されると、より力強いドラマになったのかな?という感想も持ちました)当事者が記憶を呼び覚ます危険、という事も頭に浮かびました。しかし、この映画を観たら、たまに実際聞こえてくる-居場所をバラすなんていう事がいかにとんでもない暴挙であるかということが、よくわかりますね。
しかし、杏という女性は、自らはあんなに親から酷い仕打ちを受けながら(それなりに理不尽な経緯で引き受けることになった)子どもの命は必死で守ろうとした事。彼女が実に筆マメであった事が、この悲惨な泥にまみれた物語の中に、小さな蓮の花の種が撒かれたような、そんな感覚を遺してくれたように思います。
大きくて綺麗な言葉では決して塗り潰されないドラマが、杏の姿を通して立ち上がってくるようでした。
Posted by にいさん at 2024年10月13日 14:07
前進座公演『さんしょう太夫』(別府市民劇場第124回例会)

(これから各地の市民劇場で鑑賞される方々有り。ネタバレはしないように気をつけます)
地の底から響いてくるような声が聴こえる。
説経師達の行列が、劇場の通路を埋め尽くすかの如く現れる。
この鳥肌は怖気であろうか。それとも感嘆の気持ち? 得体の知れぬその響きが、遂には舞台を埋め尽くした。
その声は、苦しみの呻きか。
恨みの心?
それとも明日への、望み。
希望とは絶望の中にこそ生まれるものだと語った劇作家を思い出していた。
中世の世に生きた民達の中で脈々と生き続けていきた物語。
それは、能に非ず、
歌舞伎にも非ず、
森鴎外の、小説にも非ず、
それは、説経節。
前進座の『さんしょう太夫』とは、そういう作品です。
この物語は元々、口伝えによって語り伝えてきた民衆の物語。それが時代を経るごとに、どこか甘い、角の丸い、御伽話のようになっていったという説あり。それはまるで世界中の名作童話がそうであったように?実際はそうではない。かつてそこにあったはずの、民衆の「怨念の調べ(水上勉氏解説より)」など無かったかのように。
かつて、説経節が伝えた物語は容赦がない。徹底的で。残酷であった。何故そこまで容赦がないのか?その意味するものを、前進座は敢えてこだわったと言います。「これは民衆の物語なのだ」と。
私が子どもの頃に児童書で読み、アニメ映画で観た「あんじゅとづし王」の物語。あらすじの大枠は違わないはずなのに。でもまったく違う。それは、切実さだろうか。その時代に生きた民の過酷な姿。生の舞台だからこそ、真に迫ってきてしまうものがあることも、確かだろう。
これが数百年の時代を超えて、ここまで既視感を持って受け止めてしまうのは、それは前進座の俳優たちの力ゆえでしょうか。うん。それはあるかもしれない。
或いは、いつの世も、さんしょう太夫は存在しているから?
後者ではないことを祈りたい。
人買いなんて、昔の話しですか?
過酷な労働による搾取、民衆からの搾取なんて。
これはやはり昔の話しでしょうか。
人買いなんてね。
また、鳥肌が立っている。なんなんだこの感じは。
読経が響き、説経師たちが再び集う。この物語は閉じねばならない。
闇がまた、劇場を包んでいった。
Posted by にいさん at 2024年10月07日 22:59
「ゴーヤーとカボスのこころ」SpaceBeppuで開催しました

10名の皆様を前に、しかも初対面や初対面に近い方も。いつもの読書会とは何もかも勝手が違って緊張いたしましたが、集まって下さった皆様!いっぺぇにふぇーでぇびる!(感謝)
ミニ講演会?私が喋るんですか?それも私自身の自分史を?
喋ってまいりましたよ。岸ママさん提唱の「人もうけ交流会」今月はなんと私上村がお話しをさせていただくことに。今、別府市で〈沖縄と大分の掛橋を目指す〉活動を始めて3年。出来る限り沖縄の話しに力点を置きつつ今の活動にも詳しく触れたいけれど時間が、なんと1時間では足りないらしいぞ(沖縄と出会うまでに辿った道のりも重要だったりするので)という想定時間はその通りだった……
頭の挨拶にウチナーグチとウチナーヤマトグチの話しを繋げて自分なりに「これはユネスコからも認められた絶滅危惧言語で日本語とは異なるルーツの言語であり専門用語では『琉球諸語』と呼ばれていること」「今もこの琉球諸語・ウチナーグチを第一言語として使っている先輩方がいらっしゃる」こと。そして「現在も県をあげてウチナーグチを大事にしていこうという取り組みに力を入れている」ことを沖縄自動車道の入口の表示の変更なども例に出して語らせていただきました(本当は方言札や日本の同化政策についても掘り下げたかった。沖縄芝居で俳優さん達はウチナーグチで台詞を言うという事も。時間とのせめぎ合いでの反省……)。とても皆様聞き上手で素晴らしいリアクションいただきありがとうございました。
しかし、まさか自分の(ざっくり急ぎ足でだけど)別府市での生い立ちについて、このような公の場で話すことになるとは夢にも思いませんでした。別府の話しも別府の話しで、とても時間内には語りきれず。しかし高校の野球部時代のエピソードめちゃくちゃリアクションいただけましたね。皆さんやっぱり野球好きですよね(^◇^;)(朝日新聞に「上村くんはキャッチボールもうまく出来ず…」と書かれたエピソードは、こういう時に使えますね〜 )
東京時代に今現在の自分の基礎となる経験が、の劇団員としての話しも「あれもこれも」話し足りないだらけだったけれど、皆さんの真剣な眼差しが熱を帯びてきて1を伝え10を感じ取っていただけた印象。感謝です。私も久しぶりに、劇団の研究所に入った時のことを話しながら記憶が鮮やかに甦ってきました。
沖縄との出会いにやっと入ったところで1時間近くなってるし(汗)焦りながら、沖縄での時間について、所々ホワイトボードにキーワードとなるウチナーグチを書きながら、もうここで出会った皆さんは兄弟・姉妹です!
反省、話し足りない話題が盛り沢山で(戦争の事、押し付けられる負担について、シビアで悲しい話しも入れたかった、けれども半端に触れるのもそれはそれで躊躇われ、そこは「この本に思いを」と。等、色々な葛藤が今も頭の中で反省会中です)実は悔しい内面を悟られぬよう、皆様の熱い感想に恐縮しきりでございました。人生で初めていただくような熱烈なお言葉に、ただただ、感謝、感謝でございますm(._.)m(1時間でももっと上手にまとめられるように、話し方をもっと磨くぞ。という決意が湧いてきたという事は、またやるつもりか?自分って、今自分に問うています)
素敵な出会いの機会を作って下さった岸ママさん、Space Beppu様、誠にありがとうございました!
Posted by にいさん at 2024年10月06日 21:15
最終週「虎に翼」

いや、ほんのわずかだろうが、たしかにここに居る。
よねと寅子のバディ感冴える最終週。時に離れた場所で、異なるポジションで、そう、原爆裁判の時もそうだ。それぞれの場所で意義のある仕事を、まるで阿吽の関係にも見えながらやり遂げていくふたり。もちろん、ふたりだけではない。俺たちの轟も、女子部のみんなも。皆で「一心同体」の気迫が、桂場等一郎をして「失敬」と言わしめたのである、と捉えてみた。
それはありふれた地獄だ。それに声をあげる事も、決して特別な事ではなかった。寅子のような「もの好きな御婦人方」と桂場が呼ぶ女性たちは現実に「ごまんと居た」のだ。声をあげる事を特別にしてしまう社会が在り続けただけであり。
それは今もか。今もなお、なのか。轟と彼のパートナーは、今の時代でもやはり、法的な関係が認められないという。寅子と航一も、遺言書を交わし事実上の夫婦とするなどという高等技術を使わずとも良い制度は、見えかけては遠ざかり、冤罪による死刑判決で人生の大半を奪われた男性の無罪が(冤罪であると)認められたばかり。寅子が、よねが、涼子が、ヒャンスクが、梅子が、人生をかけて石を穿つ以上の闘いが在ったはずだ。彼女たちの向こう側には「クソな世の中」を許さない意志が在ったはずだ。
彼女たちは「たしかにここに居る」同志と、文字通りの荒波に船を出した。最初の場面には小さな草船の映像だったドラマが、最後には、法という大きな船の話しに成長していった気がする。
憲法第14条が未だ具現化しているとは思えぬこの国で、その憲法を変えようという人間が(今も、この次の人もらしい)総理でいるという事の危機感を、ドラマの余韻と共に抱かずにはおれない。
ロスってる暇なんかあるか。お前の時代でやるべきことをやれ。と、よねなら言うであろうか。
Posted by にいさん at 2024年09月27日 20:18